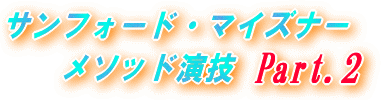 |
||
 マイズナーのメソッド演技、第2弾【基礎練習編】です。 マイズナーのメソッド演技、第2弾【基礎練習編】です。 「基礎作り・行動のリアリティ」 「感情準備」 「棒ゼリフ」 の練習についてご紹介します。 「基礎作り・行動のリアリティ」 「感情準備」 「棒ゼリフ」 の練習についてご紹介します。 |
||
「演技の基礎は、行動のリアリティである。」 最初のクラスの初めに、サンフォード・マイズナーは、この一見やさしそうなテーマを取り上げた。 「演技の基礎は、行動のリアリティである。行動のリアリティとは何かはっきりさせよう」少し間をとって、マイズナーはたずねた。「君たちは私の話を聞いているか。」 生徒たちは一斉に答えた。「はい」 「聞いているふりはしていない。君たちは聞いている、本当に聞いているというんだな」 「はい」 「それが行動のリアリティだ。疑問がないようにしておこう。もし君たちが何かするときは、本当に何かしているんだ。君たちは今朝、この教室に来るのに階段を歩いてきたと思う。ジャンプなんかしなかったし、スキップもしなかった。バレーのピルエットをしたか。いや、あの階段を本当に歩いてきたんだ。」 「では、もう少し聞いて。一人ひとり外の車の音を数えるんだ。さあ、始めて。」 20代から30代前半の、8人の男性と8人の女性の生徒たちは、ニューヨーク市内の車の行き交う音に耳を澄ました。1分が過ぎた。 「よし、いいだろう。君は何台聞こえたかな」 「いえ、まったく。飛行機の音が聞こえました。」 「飛行機は車ではない。君は一台も聞こえなかったといった。では君は、君自身になって聞いていたか。それとも、何かの役になっていたか。」 「自分自身になっていました。」 「君はどうだ」彼は、痩せた、色の黒い女性にたずねた。 「最初は、生徒として聞いていました。」 「それは生徒という役を演じていたので――」 「私は、どれが車の音かわからないので、困っていました。そのとき確かに1台聞こえました。それから、私は飽きてしまいました。その後、もう1台聞こえました。だから、私は2台聞いたことになります。」 「ここでは、飽きることは話題にしない」クラスが笑った。「・・・名前は?」 「アンナです。」 「君はアンナになって、聞いていたのか。」 「最後には、そうでした。」 「では、君の演技の一部は本物で、その三分の二はふりをしていたんだ。」 「はい」 「君は何台聞こえた?」質問は二十代後半の豊かな黒髪の女性に向けられた。 「どの音が車の音なのか、確信が持てませんでした。」 「本当に迷っていたのか、それとも役のなかで迷っていたのか。」 「わかりません。私は、ずっと何もしていないように感じていました。」 「では、君は女優として完全ではなかったんだ」それから、格子縞のシャツとジーンズの若い男性にたずねた。「君は何台聞こえた?」 「まったく。」 「まったく。では、君は・・・」 「自分自身になって、ジョンになって聞いていました。」 「それが知りたかったことだ。なかなかいいよ。」 「さて、隣に座っているパートナーを観察して、私がたずねたら、観察したことを数え上げてくれ」 十六人は、いま初めてパートナーと呼ばれた人をよく調べるために、向きを変えた。 二列目の金髪の女性は、彼女の右側の若い男性について、次のように答えた。「赤毛です。ピンクとグレーとベージュのストライプの入った落ち着いたグリーンのシャツです。サイズはМ。首に吹き出物が出ています。青い目と、短くて細い色の薄い眉をしています。小さい手。がっしりしたタイプ。かなり前屈み。ずんぐりとしている。グリーンのパンツ。ブラウンのシューズ。革でゴム底だと思います。清潔な耳とつめ。小さなくちびる。閉じられていて、下を向いている・・・」 「いいよ。その観察は、君がしたのか、それとも芝居の中の役がしたのか。」 「答えられません。正直にいって、どちらがどちらなのか区別ができません。」 「今、君は話をしている。それともマクベス婦人が話をしているのか。」 「私が話をしています。」 「それが君だ。本当の君だ。君の観察は、素直で純粋なものだった。観察は、君が行ったもので、芝居の中の役がしたものではない。」マイズナーは、格子縞のシャツを着たジョンに尋ねた。「君は今、私を見ている。」 「はい」 「オセローになって?」 「いいえ」 「誰になって?」 「自分自身だと思います。」 「そのとおりだ。そのことをよく覚えておくように。」 「質問をしたい。君たちは聞いたことを全く正確にくり返すことがことができるか。」 「私たちは、言葉をくり返すことはできます。」 「君の名前は?」 「ローズマリーです。」 「ローズマリー。『君の髪は長い』これをくり返して。」 「君の髪は長い。」 「そう、できるじゃないか。ところで、君のパートナーは?」格子縞のシャツを着たジョンが手を上げた。「では、彼女を見て、彼女について観察できることをいうんだ。彼女の精神ではなく、何か彼女のもので、君の興味を引くものだ。」 「彼女はとても――彼女はとてもフレッシュで、開放的です。」 「それは、感情の入った観察だ。私はそんなに頭はよくない。彼女がピンクのセーターを着ているのが見えるだけだ」 「わかりました。」 「いっておくが、君は考えすぎる。」 「はい。だから、ここにきているんです。」 「じゃあ、今すぐ考えることをやめるんだ。」クラスが笑った。「君は、彼女のピンクのセーターが見えるか。彼女は髪の手入れが必要だな。君は、彼女のスラックスの色がわかるか。」 「はい」 「さて、君は聞こえるといったし、くり返せるといった。それでは君は、最初に彼女のことで何か興味を引くものを探して、コメントしなければいけない。次に、ローズマリー、君はジョンのいうことをそのままくり返す。そしてジョンは彼女のいうことをそのままくり返すんだ。じゃあ、私がやめるまで、続けて。」 「君の髪は輝いている。」ジョンがいった。 「君の髪は輝いている。」ローズマリーがくり返した。 「君の髪は輝いている。」 「君の髪は輝いている。」 「君の髪は輝いている。」 「君の髪は輝いている。」 「ちがう!」二人のやりとりを止めながら、マイズナーがいった。「君たちは変化をつけるために言葉の遊びをしている。それはやってはいけない。もう一度、他に観察したことを使ってやるんだ。」 少しして、ジョンがいった。「君のイヤリングは小さい」そして、ローズマリーがいった。「君のイヤリングは小さい」彼らは、マイズナーが止めるまで、五、六回くり返した。 「いいよ。さて、わかったことは、二人とも聞くことができるし、聞こえたことをくり返すことができるということだ。これはすべてではないが、何かの始まりだ。君は彼女のイヤリングを観察し、そして、コメントをした。君は、聞こえたことをくり返した。ここまでは、君たちはお互いのいうことを聞き、聞こえたことをくり返していた。これがやってほしかったことだ。」 生徒たちはペアを組み、マイズナーが言葉のくり返しゲームと名づけた練習を何回となく行った。 童顔で金髪の青年、フィリップは、ブルネットでレイヤードヘアのサラのパートナーとなった。彼らは、フィリップがコメントした「君の目は青い」という言葉を、マイズナーが止めるまで、何度もくり返した。 「いいよ。この練習は全くばかげているように見えるだろう。しかし、これは始まりだ。君たちは、お互いに聞いているか。聞こえたことをくり返しているか。そう、君たちはやっている。」 もうひと組の生徒が、「君は明るいイヤリングをつけている」という言葉をくり返した後、マイズナーはいった。「この練習は機械的で、非人間的だ。しかし、何かの基礎だ。単調だ。しかし何かの基礎なんだ。」 アンナとパートナーが、「あなたのシャツは、明るいピンクの文字がついている」という言葉を十二回以上くり返した。「いいよ。空虚で非人間的だ。しかし、何かを含んでいる。それは関係だ。彼らはお互いに聞いていただろう。それが関係だ。お互いに聞くことから生まれる関係だ。しかし、まだ人間的な側面を持っていない。もし、ノートをとりたいなら、『ピンポンゲーム』と書いておいてくれ。これは、最後には感情を含んだ会話となる基礎なんだ。」 マイズナーは、少し間をとった。「さて、どこから問題が生じてくるのか、やって見せよう」彼は、茶色の髪を太く編んだ若い女性の方に向いた。「君は刺繍入りのブラウスを着ている。これは本当のことか。」 「いいえ」 「じゃあ、答えはなんだ。」 「いいえ。私は刺繍入りのブラウスを着ていません。」 「そのとおりだ!」マイズナーはいった。「これは彼女の見解のくり返しだ。そして、二人の人間のやりとりとなる」マイズナーはサラにいった。「君はペンを持ち歩いている。」 「はい、私はペンを持ち歩いています。」 「そうだ、君はペンを持ち歩いている。」 「はい、私はペンを持ち歩いています。」 「そのとおりだ!もうすでに、人間の会話になっているだろう。最初に機械的なくり返しがあって、次に君の見解のくり返しがあった。」 マイズナーは、豊かな黒髪の若い女性を見た。「君は髪をカールしている。」 「はい、私は髪をカールしています。」 「うん、君はカールしている。」 「ええ、私は髪をカールしています。」 「私は、『うん、君はカールしている』といったんだ。」 「ええ、私はカールしています。」 「うん、君がカールしているのはわかるよ。」 「ええ、私がカールしているのはわかります。」 「そういうふうにやるんだ。これは、君たちの見解のくり返しゲームだ。もうすでに人間の会話になっているだろう」次にマイズナーは、明るいピンクのレタリングのついたシャツを着ている、若い男性にいった。「君は私を見つめている。」 「ぼくは、あなたを見つめています。」 「君は私を見つめている。」 「ぼくは、あなたを見つめています。」 「認めるのか。」 「認めます。」 「認めるんだな。」 「認めます。」 「私は、好きじゃない。」 「あなたは、好きじゃない。」 「気にしないのか。」 「気にしません。」 「気にしないのか。」 「気にしません!」 マイズナーはその男性に向かって舌を出した。彼とクラスが笑った。 「これが言葉のくり返しゲームだ。長くやりすぎてはいけない。私は長くはさせない。さて、家で一緒にやるときは、最初にやったように機械的にやること。その後、君たちの見解のくり返しをするように。」 ◇ ◇ ◇ 「私はクラスの初めに、演技の基礎は行動のリアリティだといった。この定義は今日やってきたことと、どう関係があるのだろう。」 ジョンが答えた。「もし単純にやれば、自分自身のことに意識が向かいません。」 「君自身の外側の何かに、意識がつながるんだ」マイズナーは、つけ加えた。「他には?」 「もし本当にやれば、そのときは、自分自身がやっていることを見ている時間がありません。ただ、そのことをやる時間とエネルギーがあるだけです」 「それは君の演技にとって、とてもよいことだ。他には?」 サラがいった。「やったことはすべて具体的で実行可能なものに見えました。」 「私が頼んだことはすべて、具体的で実行可能なものだ。『具体的』という言葉は、どういう意味だろう。」 「確実なことだと思います。だれかを見て、実際にまつげの数を数えることは確実にできます。」 「何か本当に、本当に明確に存在しているものだ」マイズナーはいった。「さて、行動のリアリティとはどういう意味だろう。」 真剣な顔つきの、今まで一度も話さなかった若い男性がいった。「何かするときは、しているふりをするんじゃなくて、本当にすることです。」 「そして、役を演じているようにしないことだ。ピアノを弾くときは、最初にふたを開けるだろう。それとも、閉じたまま弾くか。つまり、音楽的にいえば、ピアノのふたを開けることは、行動のリアリティだ。他に質問はあるか。」 「あなたは、私たちが本当にできるものを与えました。他の人を観察したり、車の音を聞いたりすることです」レイがいった。「そして、もし本当に車の音を聞くことや、人を見ることに集中したら、役を演じているかどうか心配する必要はありません。集中してやっていることがあるからです。」 「それが役というものだ。」 「それが役ですか」レイがたずねた。 「そうだ。」 「そうすると、役になって演じる必要はない。何かをやっていれば、確実に役が現れるということですね。」 「そのとおり。いいか。すべての劇は、たとえばあのコメディ作家のものでさえ――何という名前だったかな。」 「ニール・サイモン」 「そう。すべての劇は、行動のリアリティに基礎をおいている。リア王が天に向かってこぶしをふるわせることさえ――俳優が自分の運命を激しく非難していることに基礎をおいている。わかるか」マイズナーは間をおいた。「今は信じられないだろうが、もっとよくわかるようになる。心配することはない。自然に明らかになる。だんだんと明確になってくる。それが演技の基礎だ。」 「何もないなんてことはない。」 「沈黙はどうですか」セイラがたずねた。 「うん、沈黙は瞬間だ。沈黙の瞬間もまた何かだ。証明して見せよう。君に才能があるか、私に聞いてくれ。」 「ミスター・マイズナー、私に才能があるとお思いですか。」 マイズナーは、顔をそむけて沈黙を続けた。クラスが笑い始めた。 「さっきのは、沈黙だったな」笑いがおさまったころ、マイズナーはたずねた。 「ええ、まあ・・・」セイラは言葉を失っていた。 「それだ。その『ええ、まあ・・・』というのが、まさに私の沈黙が、大変な表現力を持っていたという証拠だ。沈黙には、無数の意味がある。舞台では、沈黙はせりふがないということだが、意味がないということではない。」 「今日は、始め方について話をする。まず、見せたい練習がある。それは、基本的で、とても重要なものだ。そして、明らかになるものがあると思う。ジョン、立って。どのように始めるかやってみよう。この練習には、二つの基本的な原則がある。」 彼は、デスクを離れて、ジョンの脇に立った。 「『何か君たちにさせることがおきるまで、なにもするな』が、一つ目だ。二つ目は、『君たちのすることは、君たち自身が引き起こすのではなく、他の人が引き起こす』だ」 マイズナーはたずねた。 「ジョン、せりふ覚えはいいほうか。君のせりふはこうだ。『マイズナー先生』覚えられるな。一度いってみてくれ。」 「マイズナー先生」ジョンが簡単にいった。 「悪くないな」クラスが笑った。「さて、私は、何か君たちにさせることが起きるまで何もするな、といった。また、君たちがすることは、君たち自身が引き起こすのではなく、他の人が引き起こす、といった。さて、君にはせりふがある。覚えているな。」 「はい」 「何だったか、言ってくれ。」 「マイズナー先生」 「パーフェクトだ。それでは後ろを向いていただけますか。」 何が起こるのか感づいて、クラスがくすくす笑った。 「何を笑っているんだ。私は、まだ何もやっていない。」 そのとき、マイズナーは手をのばして、ジョンの背中を思いっきりつねった。 「マイズナー先生!」ジョンは飛び上がって叫んだ。笑いが起こり、ぱらぱら拍手があった。 「これが、さっき私がいったことの実例だ。『何か君たちにさせることが起きるまで、何もするな。君たちがすることは、君たち自身が引き起こすのではなく、他の人が引き起こす!』だ。」 「ローズマリー、ここにきて。」 彼女は、立ち上がって部屋の真ん中でマイズナーと一緒になった。 「せりふ覚えはどうだ。」 「すばらしいです。」 「マイズナー先生」 「マイズナー先生。私のせりふですね。」 「君のせりふだ。リハーサルをやってみようか。せりふは何だ。」 「マイズナー先生」ローズマリーがいった。 「じゃあ、原則は?」 「何かがさせるまで、何もせず、何もいわないこと。」 「何もしないことだ。いうことは気にするな!せりふは何だ。」 「マイズナー先生」 「よろしい。では後ろ向きになって。せりふに集中して、何かがさせるまで、何もしない・・・。」 なにげなく、マイズナーは、彼女の肩の付近に手をのばし、ブラウスの間にすべりこませた。 「マイズナー先生」彼女は身を引きながらくすくすと笑った。 「彼女の演技を見たかい。真実だったろう。感情でいっぱいになっていて、真実だった」マイズナーはいった。「君がくすぐったがりだとは、知らなかったよ。」 笑い声が教室に響いた。 「さて、ぼくは、基本的で、技術と有機的な関係をもつものについて話し、実例を見せている。君たちは、いままで何を見てきた。」 「ぼくは、本当の受け答えを見ました」ジョゼフがいった。 「何について。」 「あなたが、つかんだり、つねったりしたことです」 「要するに、私がつねったことは、彼の悲鳴を正当化するんだな?」 「そうです」 「彼の悲鳴は、私がつねったことの直接的な結果だった?」 「はい」 「原則は、何だ。」 「何もしないこと・・・。」 「何かが起こるまでだ。彼に何かが起こった。彼女にも何かが起こった。自然発生することが、ここではかかわりをもっている。いいな。ほかには?」 「真実であることです。」ジョゼフが答えた。「それは真実になるための基本です。」 「そうだ」マイズナーがいった。 「ジョゼフ、選んだ作業をやってくれ。」マイズナーはジョゼフを見つめた。「君は何をやるんだ。」 「ぼくの作業の理由を知りたいんですか。ぼくの甥が病気で入院しようとしています。ぼくは彼のためにまんがを描いて、恐がることはないことを説明してやろうと思っています。」 「よし、命がけでやるんだ。私がノックする。私と君でくり返しをやろう。」 ジョゼフは、まんがを描き始めた。マイズナーはジョゼフが作業に没頭したのを見て、机の上をノックした。 「何か用ですか」ジョゼフは顔を上げながらたずねた。 「君はその作業を続けなくちゃいけない!」マイズナーは大声をあげた。 「わかってます」ジョゼフがいった。 「じゃあ、やるんだ。」 ジョゼフは仕事に向かった。マイズナーはじっと彼を見つめた。「何をやっているんだ。」 「何をやっているかですって?」ジョゼフは、マイズナーを見上げながらくり返した。 「なぜ見上げるんだ。」 「なぜって、あなたが何をしているか見るためです。」 彼は再び描き始めた。1分が過ぎた。「忙しいのか?」マイズナーは何げなくたずねた。 「忙しいです。」 「忙しいのか。」 「忙しいです。」 再び間があいた。マイズナーはジョゼフに一歩にじり寄った。「とても忙しい」マイズナーは感嘆するかのようにいった。 「とても忙しいです。」ジョゼフは認めた。 「忙しい。」 「ええ、忙しいです。」 「ええ」 「ええ」 再び沈黙があった。マイズナーは一歩進み、座っているジョゼフを見下ろすようになった。「私も忙しい」 「あなたがですか」ジョゼフは、デッサン用のボードに屈み込みながらいった。 「ああ、私はとても忙しい」マイズナーは、ジョゼフの肩にかぶさるようになりながら答えた。 「あなたはとても忙しい」ジョゼフはいった。それから、いらだちのあまり立ち上がり、いった。「ぼくの仕事を邪魔しているのが、わからないのですか!」 「だから、私は忙しいんだ!」マイズナーは誇らしげに、大きな声を上げた。クラス中が笑った。「さて、どういうことがわかったかな。」 「やることを本当にやることです」ジョゼフがいった。「あなたはぼくの邪魔をすることで忙しかった。ぼくはこの仕事をやると同時に、あなたの相手もしなければいけなかった。」 「わざと、それとも本当に。」 「本当にだと思います。」 「先週、私はセイラに何といったかな。セイラ、私は君に何といった?」 「沈黙の瞬間は何もないのではない」彼女が答えた。「それはやはり瞬間だ。」 「それは何か意味あるものだ。そうだな。演技は話すことではない。他の人を使って生きることだ。どういう意味かわかるか?」 「演技はおしゃべりではない」べスが答えた。「他の人に真実に反応することです。」 「そうだ。ジョゼフ、要約してくれないか。」 「意味は行動の中にある。行動が君たちに何かをさせるまで、何もするな。」 「そして、何かをするときは、どういうふうにするんだ?」 「真実に、十分に、そのことを本当にやります。」 「やってみるんだ!」 「やらなくてはいられなくなったことをすること。」 「やらなくてはいられなくなったことをすることだ。さて、ジョゼフ、君のやっていることには良い点がある。それは、その作業が特別で、君にとって意味があるということだ。まちがっている点は、少しずつ直ってきてはいるが、話し続けなければいけないと、まだ君が思っていることだ。その反対はなんだ。」 「話すことの反対ですか?沈黙です。」 「沈黙。君たちに何かをさせることが起こるまでだ。」 「ライラ、私たちがここでしなければならないことは、論理を遠ざけることだ。なぜなら、くり返しは本当の感情を引き起こすが、論理は知的なものにとどまるからだ。わかるか。」 「はい」ライラがいった。金髪に染めた四十代後半の女性。彼女はもっとも年輩の生徒だ。 「さて、君には多くの経験がある。今まで君が台本を手にとるときは、これは私の想像だが、ここはこの感じとか気分とか、君が考えたものにしたがって読む傾向があった。これは君の意志だといっておこう。ところで、私はその習慣をやめさせようとしている。簡単なことだ。ばかみたいに、くり返すんだ。何かが君に起きるまで、くり返しをすること。君自身から出てきた何かが起きるまでだ。いいか」 「はい」 「しかし、君がやったようにパートナーにたて続けに質問するのは、頭を使っているからだ。私がやろうとしていることは、君が頭を使わないようにすることだ。いいか。」 「頭を使わないようにします。」 「何を使うんだ。」 「私の感情。」 「指してみて。」 ライラは、胸を指した。 「そのとおり。私の第一歩は、いろいろと指摘をすることを君にやめさせることだ。私がいったことをくり返して。」 「あなたは論理を使うことをやめさせて、私の――」 「君の衝動だ――」 「私の衝動と本能。本当にそれだけを使えたらいいのですけど。」 「今日、二分間使おうとしたら、明日は四分間使えるようになる。わかるか。」 「はい、やってみます。」 「もちろん、君はやると思うよ。くり返せ、くり返せだ。」 十一月二十八日 アンナとビンセントは、両方ともパートナーが欠席をしていたので、一緒に練習することになった。ビンセントはひとりでやる作業を持っていた(オーディションに備えて台本を覚えるというものだ)。 アンナがノックをして部屋に入る。彼女が出て行く前にマイズナーは、彼女を呼んで、耳元にささやきながら、簡単な指示を与えた。 この指示が練習に与えた効果は驚くべきものであった。 アンナはかんかんに怒って部屋に入ってきた。彼女が怒っている本当の理由は語られていなかったが、彼女の行動からビンセントが彼女を中傷したと思っているのは明らかだった。彼女は激怒していて、ビンセントはほとんど何もいえなくなっていた。マイズナーは喜んだ。 「いいよ」アンナがバタンとドアを閉めて出て行ったとき、彼はいった。「とてもよかった。さて、今のは全く基本的な練習だった。しかし、何かが加えられていた。それは何だろう。」 ベティがいった。「彼女は怒って入ってきました。」 「感情的な状況だ。私は演出家として、感情的な状況を練習に加えた。そして、練習はシーンとなった。練習の中では、覚えたせりふはない。今、君たちはせりふを覚えている過程にある。その過程の中で欠けていたものがある。それが今、私たちが見たもの――感情的な状況だ。」 ジョゼフがたずねた。「サンディ、何が欠けていたのか、もう一度いってください。」 「君たちが今、せりふについて学んでいる中で欠けていたものは、感情的な状況と関係のあるものだ。」 「あなたは、私たちがせりふを機械的に覚えることについて話しているのですか。」 「そうだ。やがて・・・それはとても難しい感情準備の問題にいたるのだが、それはクリスマス・プレゼントにとっておこう。」 「少し話をしよう。」 マイズナーは、ローズマリーとジョンのシーンを止めた。彼らは覚えたせりふを静かに、しかし人間の会話のように話していた。 「私たちが求めているのは、きっかけのせりふではなく、衝動を拾い上げることだ。人はきっかけのせりふは、拾い上げない。衝動を拾い上げる。やって見せよう。とてもシンプルで、とても即興的だ。ジョン、私に何を飲みたいか聞いてくれ。それから、スコッチ、ウォッカ、バーボン、ジン、それといろいろな清涼飲料水があるといってくれ。」 「サンディ、何か飲みますか。スコッチ、ウォッカ、バーボン、ジン――」 マイズナーは、スコッチという言葉を聞いて、目を輝かせ、右手を上品に動かして、ジョンの説明を止めていった。「スコッチをください。」 クラスが笑った。 「さて、いつ衝動は起こっただろう。」 ローズマリーがいった。「スコッチです。」 「最初にだ!衝動を拾い上げるのと、きっかけのせりふを拾い上げるのは全く違う。」 「そうすると、もし衝動が最初に起きたとする、彼が話し終わるまでそれを保って、それから『スコッチ』といえということですか。」 「きっかけのせりふがくるまでだ。きっかけのせりふは拾い上げない。衝動を拾い上げるんだ。」 ジョンがいった。「衝動とうまく同調するためには、もっとよく台本を知っていなければいけないということですね。」 マイズナーがいった。「全くそのとおりだ。しかし、最初にしては悪くない。それは、台本が自分で解決していくことだ。ローズマリー、君はなぜノックした。」 「練習のためにそうすることになっているからです。」 「君はここで生きているんだ!」 「わかっています。私たちがやっていることについて、まだ少しはっきりしないことがあります。これは練習ですか。シーンですか。」 「即興的に扱われるシーンだ。衝動から衝動へと。」 「私は彼の行動に感応するんですね。テキストではなく。」 「両方だ。じゃあ、君のためにやって見せよう。君のせりふは『あなたは意志が弱い。百歳になるまで二度とアルコールは口にしないと約束したのに。もう約束を破ってしまったのね』だ。そして、私のせりふは『私は弱くない』だ。さて、いつそのせりふのための衝動が起きるのだろう。そう、最初だ。きっかけを拾うな、衝動を拾え。君のせりふをもう一度いって。」 「『あなたは意志が弱い。生きている限り二度とアルコールは口にしないといったのに、その約束さえ守れない』」 「『私は弱くない』私は、君が話し終えるまでずっと演技をしていたんだ!わかるか。」 「あなたはパートナーがせりふを終わる前に、私たちのせりふを始めろとはいっていないのですね」 ベティがたずねた。 「いっていない。きっかけのせりふを待てといったはずだ。しかし、衝動や感情は感じたときにいつでもやってくる。台本を使いこなせば、すぐ慣れる。私は二つのことをいっている。『せりふを覚えろ』と『衝動を拾い上げろ』だ。」 「とてもよかった。」 ジョゼフとベスは彼らのシーンを終えたばかりだった。 「さて、まもなく――できればクリスマス休暇の前に――感情準備という困難な問題の要点を教えようと思う。感情準備は自分で感情を刺激することだ。それは演技の中で最も微妙な問題だと思う。そして、私たちはいずれこの問題に入って行く。しかし、今日はまだ入らない。次回は二つのものを加えてこのシーンを終わる。ジョーは惨めな気分でやる――何をやってもいい。そしてベスは晴々とした気分でやる――何をやってもいい。私は感情準備を期待している。」 |
||
「今日は感情準備について学ぶ」マイズナーがいった。 「感情準備は、君たちがシーンや芝居を感情的に生き生きとした状態で始めるためのものだ。それは、君たちが感情的に空っぽの状態で舞台に出ないことを目的としている。このテーマについて、私はいつも単純でありたいと思う。 シェパード事務所で、すばらしい芝居のすばらしい役の契約をしたとしよう。書類に名前を書き込むとき、君たちには喜びが込み上げてくる。たとえ地下鉄で四十五分もかかるリバーデールに住んでいても、シェパード事務所でいっぱいとなった喜びと誇りは、家に着く頃になってもある程度残っている。はっきりしない点があれば質問してくれ。」 彼は間をとったが、生徒たちは彼のいっていることを理解していた。 「スタニスラフスキー・システムの初期に、彼は本当の行動を探していた。たとえば、大きな喜びが欲しいとしたら、大きな喜びのリアリティを何から求めるかを考えた。彼はこれを『感情の記憶』と呼んだ。 私はこの方法は使わない。スタニスラフスキーも三十年間の実験の後で使わなくなった。 理由か? たとえば、君たちが二十歳で、デリカテッセンで働いているとしたら、ソフィア・ローレンと過ごしたすばらしいひと夜のことを思い出せる可能性はほとんどない。そのような美化されたセックスの喜びを、君たちが知っている可能性はほとんどない。私のいっていることが分かるか?」 クラスは頷いた。 「別ないい方をすれば、君たちが探しているものは、必ずしも実人生のリアリティに限る必要はない。それは想像の中に見つかるかもしれない。抑制もなく、礼儀作法にもとらわれず、自由に実際ソフィア・ローレンのことを想像するとしたら、君たちの想像はおそらく本当の経験より深く説得力のあるものとなるだろう。わかるか。私がいっていることを誰か説明できる人はいるか」 ジョンが手を上げた。 「私たちの想像は、私たちが思い出す過去の経験より強いとはいわないまでも、同じくらい強いということです。」 「そうだ。ローズマリーは?」 「たとえば、私が肩から大きな重荷がとれたような感じを得ようとしたら、こういうのを使えますか。『これから十年間は働かなくていいんだわ。――宝くじに当たったのよ』つまり、ベーコン・チーズバーガーを売るのにうんざりしていて、突然それから解放されて、喜びに泣いてしまいそうだというような私の実人生の状況を使ったほうがいいのでしょうか。」 「君を動かし、影響を与えるものを使ったほうがいい。」 「ということは、私はシンデレラになったふりをしなくてもいい――」 「しなくていい!」 「あばら家に住んでいて、いつもガラスの靴をほしいと思っているふりを――」 「しなくていい。しかし、もしあばら家に住んでいて、最後にガラスの靴を手に入れることが君の感情を引き出すなら、使ってもいい。私がいっていることは――あまり難しく考えないでくれ――空っぽのまま舞台に出てくるなということだ。内面の状態を、与えられた状況が思いつかせるものから作ること。これは感情を自分で刺激することと関係がある。私が願望について君たちに考えさせた理由は、君たち自身の中に君たち自身にしか属していない要素を見つけてほしかったからだ。 さて、その内面の状態を見つけるよりどころは、そのシーンの必要性と必ずしも関連していない。十九世紀のイギリスの俳優、ウィリアム・チャールズ・マクレディは、『ベニスの商人』の1シーンを演じる前に、レンガの壁に埋め込まれた鉄の梯子をいつも舞台裏で揺すっていた。彼は何回もやってみたが、少しも動かないので怒ってしまった。そして、それから舞台に出て行って演技をしたんだ。わかるか。」 「あなたのいっている感情準備は、必ずしもシーンと関連しなくていいということですね」レイがいった。「マクレディの場合は、梯子に怒ってから、ラブシーンを演じるために出て行ったのかもしれません。」 「彼は梯子に怒ってから、ラジオ・シティの前で一時間半も女の子に待たされたというシーンを演じるために出て行ったのかもしれない。それは可能だ。私は君たちに『空っぽのまま出てくるな』という前提を話している。いいな。」 「私を刺激するものは肉体的なものです。ハンバーガーや知的なことを考えることは、私を動かしません。」 「君たちは、君たちを刺激するものを探さなければいけない。」 「それが感情準備だ!」
|
||
「今日は、驚かすものがある――台本だ、時代遅れの骨董品だけど。しかし、シーンの一つひとつには、心を動かさずにはいられない人間の問題が含まれている。これが、これらのシーンを私が選んだ理由だ。みんなは、意味をとったり、解釈したり、注釈をいれたりしないで、台本を覚えてほしい。機械的にせりふを覚えるだけだ。はっきりさせておこう。『生・き・る・べ・き・か・死・ぬ・べ・き・か・そ・れ・が・問・題・だ』」 マイズナーはこの有名なせりふを淡々と暗唱しながら、机の上を音節ごとに手で叩いた。 「つまり、脚韻なんか踏まない、ただの冷たいテキストだ。そして、それを機械的に覚えたら、気楽にパートナーと散歩でもすること。どこを歩いてもかまわない。そして、もう一度テキストを、最初からやってみる。もし立ち止まってコーヒーが飲みたくなったら、かまわないから飲みながらやっていい。そして、店員たちを驚かしてやるんだ。『あいつら自分のいっていることがわかってないんじゃないの!ロボットみたいにしゃべっているぜ!』ズボンが脱げるほど彼らを驚かしてやるんだ。」 十一月二十一日 淡々と機械的な精密さで。ジョンとラルフは『ミスター・ロバーツ』の1シーンを暗唱したところだった。 「いいよ」マイズナーが話し始めた。「彼らはひどく奇妙な言い方で、せりふをいった。そうだな。そこには意味もないし、解釈もない。この機械的な暗唱法から、人間的な経験を得ることは何もない。さて、私がいっていることに疑問を感じている人はいるか。ベティ、君の疑問は何だ。」 「ブルースと練習しているとき、ふっと感じたことがありました。機械的な暗唱法でやると、それが生のままで加工されていないので、感情を無制限に加えられると思います。なぜなら、ある種の解釈に安易に固執することがないからです。」 「いいことをいうな。『生のまま』そうだ。『生のまま』だ。私は、計算された結果を避けるために、この機械的な取り組み方にこだわっている。ジョン、何かあるか。」 「ぼくには難しいと思います」ジョンがいった。 「君には難しいのか。」 「ここにくる途中、練習してきたんですが、ラルフがときどきいうんです。『君は解釈している。それは解釈しているんだ』ぼくは、これまでずっとやってきたパターンに、おそらく落ち込んでいるんです。」 マイズナーが答えた。 「そのとおりだ。私は、いま君がいった、俳優人生の中で身についた君の癖を取り除こうとしている。私は、君自身の中から、せりふの感情的な把握から出てくる演技を作り上げようとしている。そのために君を無色で、意味をもたず、非人間的なものにすることにした。ロボットと呼んでもいい。そのせりふを感情面の真実で満たすためには、君は、最初はせりふを淡々と、表現をつけず、完全に無色な方法で覚えなければいけない。」 「見せたいものがある。ジョン、ここにきて。」 ジョンは席を離れて、机の側に立った。マイズナーは机をまわって、彼の側に立った。 「じゃあ、むこうを向いて。体をできるだけしっかりと固定させるんだ。必要なら机をつかんでもいい。とにかく体を全く動かないようにしてくれ。」 「わかりました。」 「まだ充分固定していないようだが、大丈夫か。」 「ええ」 マイズナーは、両手の手のひらをジョンの肩において、動かそうとした。「私は彼に何の効果も与えられないようだ。もう一度やってみよう。ジョン、同じことをやってくれ。」 再びジョンは机の縁をつかんだ。あまり強くつかんだので、こぶしが白くなった。 マイズナーはいった。「彼は硬直している!」そして、それからつづりをいった。「こ・う・ち・ょ・く」クラスが笑った。「さて、ジョン、リラックスして。」 ジョンは机から離れて、肩や腕を回したり振ったりして、緊張をほぐした。マイズナーは、しっかりと、しかしやさしく押した。ジョンは大きく、ゆっくりと二歩踏み出した。 「彼は反応している。わかるか。リラックスだ」マイズナーはもう一度押して、ジョンはまたゆっくりと歩いた。 「彼は私のしたことに反応している。ありがとう、ジョン。座って。さて、もし君たちが無色なら・・・無色とはどういう意味だろう。影響を受けやすいということだ。もし無色なら、君たちは感情に対して適応力を得ることができる。そうだな。もし緊張して、リラックスしていないと、最初ジョンがそうだったように、君たちは私の押しの影響に反応することができない。結論として、論理的なことがいえる。『テキストにできるだけ意味を持たせず、リラックスして覚えること。そうすれば、どのような影響も受け容れられる』この論理がわかるか。わからなければ、いってくれ。」 フィリップがいった。「無色でリラックスしていること。堅く緊張していないこと。」 「構えず、固執しないことだ。私がいっているのは、俳優としてせりふや言葉を学ぶときはいつも、私が押したときのジョンのように、空っぽで、固執せず、リラックスして覚えることだ。何か質問があるか。これが、私が機械のような精密さでせりふを覚えるように頼んだ理由だ。機械的精密さ、そこから私たちは先に進む。」 フィリップがたずねた。「もし自分が言葉を解釈したり、何か付け加えようとしていると気が付いたら、ペースを落としたり、やめたりできますか。」 「やめることだ。君にせりふをあげよう。『おお神よ、私の魂は血を流しています』さあ、聞かせてくれ。」 フィリップはいった。「おお神よ、私の魂は血を流しています。」 「では、表現をつけてくれ。」 「おお神よ、私の魂は血を流しています」フィリップは少し声を大きくしていった。 マイズナーはいった。「もっと!君は神を信じていないのか。それと痛みも忘れるな。」 フィリップは吼えた。「おお神よ、私の魂は血を流しています!」 「それが、私が君たちにやってほしくないことだ。わかるな」マイズナーはせりふを静かに機械的に暗唱した。「『おお/神よ/私の/魂は/血を/流して/います』最後には、このせりふは君たちの心の中から出てくるようになる。」 マイズナーは、デイブを止めた。彼がせりふを奇妙な読み方で読んでいたからだ。彼のいつもの傾向なのだが、やりすぎていた。彼の読み方はあまりにも機械的になっていた。 「デイブ、私が君にいったことを説明してくれ。」 「機械的に、無色に、くり返してほしいということです。」 「そうだ。」 「ぼくはやりすぎています。」 「どんなふうにやりすぎているんだ。」 「音節ごとに機械的な性質を強調しすぎています。」 「そうだ。私は君のくり返しについて何といった。」 「ぼくが相手の行動を拾い上げていないこと。くり返すためにくり返しているにすぎないということです。」 「今やっていることも同じじゃないかな。つまり、君は機械的な部分を少しやりすぎているんだ。」 「ぼくは練習を学問的にやっていました。あなたは、『くり返せ、くり返せ』といつもいっています。そして、ぼくはほとんどそのことだけに気を使っていました。練習を学問的にやっていて、瞬間瞬間あるがままにしていませんでした。」 「学問的という言葉はいい言葉だ。」 「この練習は、とても難しいと思います」デイブのパートナーのジョゼフがいった。 「難しい?なぜだ?」 「私たちは言葉をいい方と合わせて覚えます。『やあ、こんにちわ』というふうにです。もしいい方をすべて取り除くと、私たちは足場をなくしてしまいます。」 「そうだ。君が機械的に、また解釈なしに文章を完全に捉えるまではだ。」 「しかし、私たちはみな感情を使って記憶し、言葉にある重要性を持たせます。だから、覚えることができるのです。だから、記憶するときはある抑揚が伴うのが普通です。」 「それは耳の中に残っている抑揚だろう。このようにやることで、それを取り除くことができる。それは君にとって、どんな価値があるだろう。」 「ええ、あらかじめ獲得している感情の結びつきを取り除くことができます。そして、いったんこのように文章を覚えてしまえば、感情はパートナーが与えてくれるものから出てきます。」 「他に気がついたことがあるか、ジョン?」 「この練習から得られるものは完全で、正直なものだと思います――」 マイズナーは割り込んだ。「そして即興的だ。これは、やがて即興になる。基本的には即興はとても健全なものだ。それは君たちの過去の習慣を取り除いてくれる。」 |
||
 Part.3 は、実践練習編だよ。 Part.3 は、実践練習編だよ。
|
||
 |



